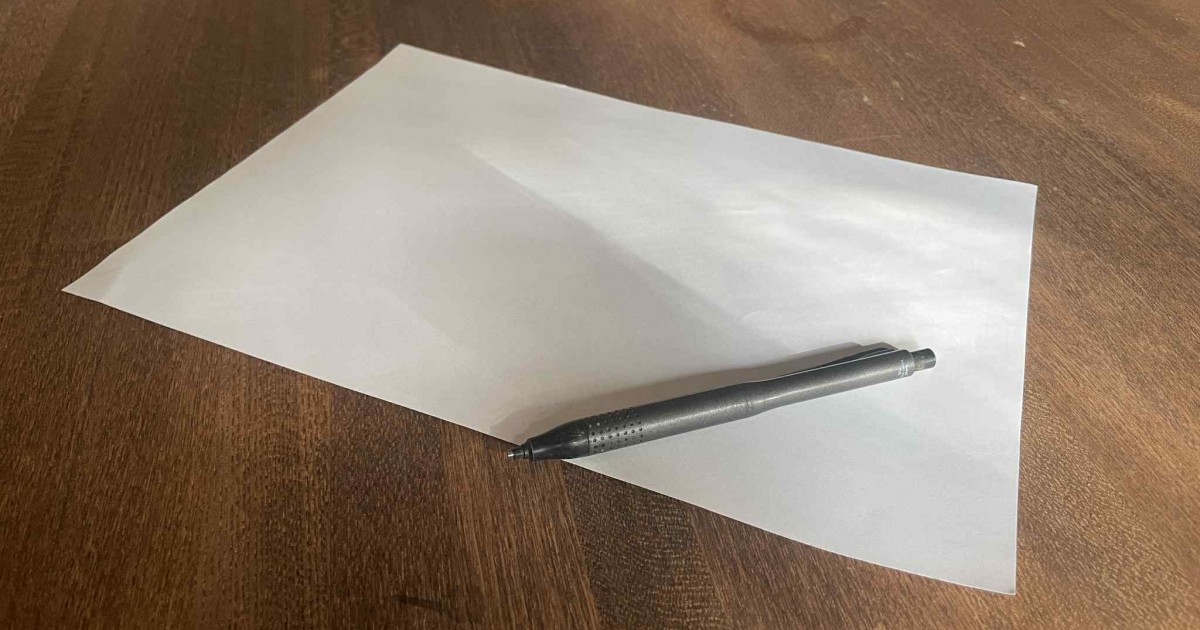好きな作家に出会いました。ケン・リュウさん
最近のこと、「ああ、僕はこの作家が好きだ。」という出会いがありました。中国系の作家、ケン・リュウさん。「中国」や「中国人」について、SNSで否定的なニュアンスの発信を毎日のように目にするけど、この人の書く中国の人たちの心、みたいなものはとても繊細で傷つきやすくて美しいと思ったのであります。
ケン・リュウさんの作品との出会いは偶然でした。
ワタクシ、近年は割と人の勧めだったり、自分の興味だったりで目的をもってオンラインで本を買うことが多くなっております。でもやっぱり、本屋でふらふらとあてもなく立ち読みしながら、「なんとなく」の一冊を買う、という行為が好きなんですよね。
だから本屋さんを街で見かけると積極的に入るのですが、大型の書店はどうにも疲れてしまう。平積みになった売れ筋の本の、「この本はこんなにも素晴らしい内容ですよ!」「あなたにぴったりですよ!」という自己主張の強い帯の数々にエネルギーを吸い取られてしまいます。新しい出会いのワクワクの前にヘロヘロになって、結局何も買わずに本屋を出る、ということを繰り返してしまうのです。
友人の野村浩平さんの個展が開かれるということで妻と一緒にいった東中野の書店、platform3 がケン・リュウさんとの出会いの場です。非常に素敵な心地よい書店でした。駅前の小さな雑居ビルの4階。いかにも中央線カルチャーという感じ。事前情報がないとそんなところに書店があるなんて知るすべもないような立地。
書店の壁面に飾られた野村さんの作品や言葉たちを味わいつつ、そのまま、地続きでplatform3の本たちを見入ってしまいました。先に書いたような「買ってください!」の主張がほとんどない。ほしかったらどうぞ手に取って、という控えめな感じで置かれた本たち。それでもそこには選んだ人の世界観が現れる本たち。ジャンル分けも曖昧で、ふわふわと様々なテーマが連なっている各国の本たち。ああ、気持ちいい。ああ、楽しい。
小さな室内を何周も何周もグルグル回ってしまいました。
目についた本を手に取ってみてはパラパラ。またフラフラと棚をうつろって、またパラパラ。あっという間に時間が過ぎていきました。ここでしか手に入らないであろう本も色々とあったのだけど、最終的には普通にアマゾンでも買えるであろう文庫本を2冊、そのときの気分で買いました。
その一冊がケン・リュウさんの短編小説集「もののあはれ」でした。
この人の名前をどこかで聞いたことがあった気がするのだけど、それがどこだか思い出せない。ハヤカワ文庫っていうとSFってイメージが強いけど、ワタクシ自身、SFが特別好きなわけでもない。しかもそもそも、ここ最近は小説はあまり読んでいないし、下手すると最後まで読み通せないことも結構あるのだけど、短編の気楽さがあったのか、なんとなく、偶然の出会いに任せて買ってみました。
結論、ものすごく素晴らしい出会いになりました。ケン・リュウという作家が好きだ、と強く思いました(そういえば、作家が好き、という風に思うことって久しぶりな気がする。学生の頃は『好きな作家』がいっぱいいた気がするけれど、最近はあまりそんな風に感じることがなかったような…)。そして、生まれて初めて、勢いに任せて公式サイトから本人にファンレター的なメールを送ってしまいました(生成AIの手を借りて自分の言葉を英訳しつつ)。
この人の書く物語はすこし痛くて、悲しくて、寂しくてそれでも温かくて、優しい。
ケン・リュウさんは8歳まで中国で過ごしたのち、アメリカに家族で移住したという人。1976年生だということだからほぼ同世代。多感な時期にアメリカでマイノリティとして過ごした傷みたいなものと、幼少期に過ごした中国の原風景みたいなものが混ざり合って、作品のうちに漂っている気がします。その儚さ、白黒はっきりしない感じがとっても心地いいのです。
そこにはなんというか、僕自身が「日本的」と感じるような心象風景が漂っていて、非常に心動かされます。
SNSで日々、目にする否定的なニュアンスでの「中国が…」「中国人が…」というひとくくりの言説では見えてこないもっとゆるやかな風土、自然風景としての「中国」とそこに暮らす人々の心の内側が漂っていると勝手に感じました。それは優しく、暖かく、懐かしく。対立軸としての“中国”ではなくて、この日本と文化的につながりのある東アジアの原風景としての中国、その暮らし、そこに住まう人たちの心のあり方、みたいなものが感じられます。そして、それらに共鳴している自分がいます。
もちろん、彼の作品はフィクションなわけだけど、だからこそより一層、そこに漂う気配が伝わってくるのでしょう。
日本ではハヤカワ文庫から短編集が6つ出ているようです。私は、この時に買った「もののあわれ」という短編集と、帰宅後にアマゾンで買った「紙の動物園」の2冊を読了しました。つづいて3冊目「母の記憶に」も手配中。この文庫版シリーズの装丁も素敵だし、日本語訳も心地よく、久しぶりに気持よく小説を読んでおります。読書の秋、バンザイ。皆さんもよかったらぜひ。
2冊のなかでとりわけ印象に残った物語、「文字占い師」のなかで中国人の老人が語った言葉が印象的だったので最後に引用します。
“日本”や“中国”は存在していない。それらはたんなる言葉に過ぎない。絵空事だ。個人としての日本人は偉大であるかもしれず、個人としての中国人は何かを欲しているかもしれないが、“日本”あるいは“中国”がなにかを望んだり、信じたり、受け入れたりできるだろうか。いずれもたんなる空虚な言葉に過ぎない。神話だ。
すでに登録済みの方は こちら