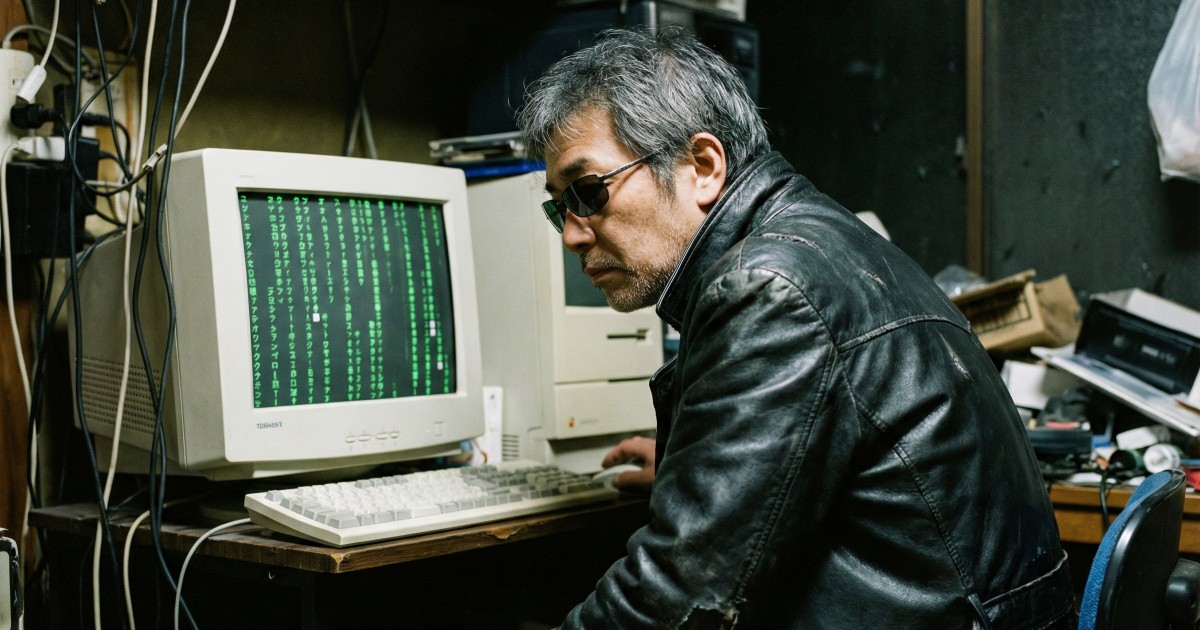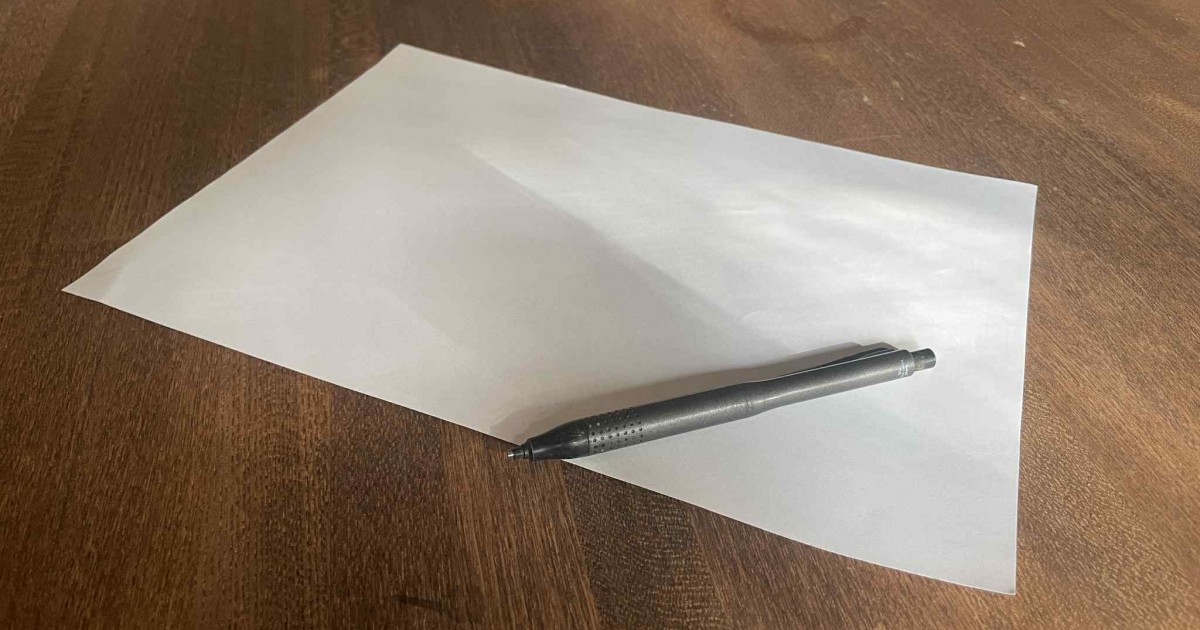生成AI時代を生きる僕らの大切な「技術」。
この2カ月、熱に浮かされたかのようにAIに没頭してきました。この週末にすーっと落ち着いてきて、AIデジタルワールドと身体ワールドのバランスが取れるようになってきた気がします。そんな中、いくつかのやり取りから浮かび上がってきた僕らの大切な「技術」について書きます。
先日のことです。ワタクシが理事を務めさせていただいている一般社団法人みつかる+わかるの理事会がありました。新任の理事として初めてお会いした人類学者の比嘉夏子さんが教えてくださった「人類学的アプローチ」の話が大変面白く、ヒントをたくさんくださいました。
「自分の中を通す」のが人類学的アプローチ
以下、比嘉さんのお話を受けての私の理解です。(あくまで私の理解なので、間違っていたらごめんなさい。)
人類学というのは現場の学問であり、フィールドの学問であると。研究対象の現場に入り込み、時間をかけて一緒に生活し、言葉を交わし暮らしに溶け込むなかで、自分の内側での気付きを言語化し、抽出し、形にし、比較し、研究する学問なのだそうです。
比嘉さんはトンガで長年、フィールドワークをしてきたそうで、一時帰国した際に空港に迎えに来られたお母様が比嘉さんを本人だと気付かなかったらしいです。自分の気配が変わってしまうぐらい、溶け込み、交わる学問が人類学のアプローチだそうです。
比嘉さんは身振りを交えて伝えてくださいました。「いったん、自分の中を通す」と。
なんという捨て身の学問!下手すると自分のアイデンティティが崩壊しそう。まるで役者やイタコのような仕事だなと思いました。
取り込んだものをアウトプットする手法は明確にあるのだけど、どうやって自分がそれをできているのか言語化できない、と比嘉さんはおっしゃいました。これ、すごい技術だと思うんです。名づけて「いったん、自分の中を通す技術」。
揺れ動く不安定な「知」こそ希少になる
日々、生成AIを触る中で思うのですが、この「技術」こそ、生成AIが浸透する社会においてとても希少で大切なものになるんじゃないかな、と思い至りました。(ここから先は私が考えたことで比嘉さんの言葉ではございません。200%ワタクシの想像でござんす)。
確からしい答えにたどり着くこと、情報を比較検討すること、膨大な情報を調査・統合して分析すること、その情報を分かりやすく整理して伝えること…、など仕事をするうえで大切だと言われてきた「技術」の多くは、生成AIを利用することでいとも簡単に手にすることができるようになりました。この流れは加速こそすれ、後戻りすることはなさそうです。
そして、今は一部の人だけが使っているものだとしても、すぐに一般化して、先に書いたような思考力・論理力・分析力的なものは生成AIの浸透とともに誰もが普通に扱えるスキルになっていきそうです。
その世界で生成AIには難しいオリジナルな「知」をアウトプットする技術として、重要になってくるのが「いったん、自分の中を通す技術」なのだと思います。なぜならば、いったん“自分”の中を通ったものは生成AIが抽出する「一般的に共有される、正解への最短距離を示す分析的な知」とはまるで違うものだからです。人間の中を通ったものは個別性があり、偏りがあり、曖昧であり、揺れ動くものとなるでしょう。
そんな不安定で面倒な人間的な「知」はきっと希少になる。
稚拙で具体性を欠いたっていいのだ
では「いったん、自分の中を通す」ってどういうことだろう?
いくつか要件がある気がするので言葉にしてみます。
①一定の時間をかける(時間がかかる)
②文字や映像からの視覚情報だけでなく、環境に身を置き、全身で受け取る
③思考だけではなくて、身体感覚や感情に入ってくるものも受け取る
④そのうえで、自分が受けた影響や変化をちょっと冷静にながめて取り出す
youtubeやウェブの検索や教室で知識を得るのとはまったく異なるアプローチ。時間がかかって、ときにしんどさや痛みを伴う営み。どこにもたどり着かないかもしれない不安が伴う作業。あるいは自分の恐れや触れたくない感情が湧いてくるかもしれない。
そうやって身体と心を張って時間をかけて得られる知恵は、生成AIが瞬時に辿りつく正確無比な調査結果や提案よりも曖昧で稚拙で不正確で、具体性に乏しいかもしれません。そして、圧倒的に効率が悪い。面倒くさい。時間がかかる。
だから、価値があるのだと思う。みんなやりたくないから。やらないでも生きていけるから。今、この瞬間も「いったん、自分の中を通す技術」は非常に価値があることだと思うけど、先に書いた社会の変化によって、回り道と手間を厭わない気概がさらに大切になるのだと思います。
自然にダイブすることで紡がれる言葉の尊さ
先日のこと。
原っぱ大学の「おとな学部」で三浦半島の山の中に探検に行きました。
標高100mもない小さな山。大人ばかり数名で道なき道を切り拓いて、崖を這いつくばって、その山の稜線にたどり着いて、反対側に降りていくと名もなき小さな沢の水源にたどり着いて。その沢をくだってひたすら歩くといつしか街にでて、最終的に海に出ました。
大人だけの小さな小さな数時間の冒険。身近な山の中にはいって、山と、川と、海を感じた時間。
参加者のひとり、ゆりさんがSNSにこんな言葉を投げてくれていました↓
(前略)日常生活の中で『無い』ことに目を向けがちになる自分に『もうすでに在る』ことを教えてくれる自然
自然相手は危険が0ではない環境の中で五感をフルに研ぎ澄まして集中して探検することで頭が無になってスッキリする感じ
コースを進んでいてもスルスル行ける人と私のように行けない人がいた時、この違いは何か?と少し広い視野で見てみると、私は目先、上手な人はもう少し先を見てる。これって私の生き方にも似ているなって笑けてきたり…
ここ最近、私1人だけではどうしようも解決できないお悩みに直面していたけれど、悩み相談をするわけでもなく、この大自然と一日中探検していたら少し答えが出てきたような気がしたな…(後略)
これぞ「いったん、自分の中を通す技術」の結晶。
一人では分け入らない山の中に問答無用で連れていかれて、ただその時間を味わって、ときに怖さで身体がすくんだり、予想外にずぶ濡れ、泥んこになって気持ちが萎えて…、それでも無事に帰ってこられたときにアスファルトの道路の有り難さを実感して…。
そのひとつひとつを全身全霊でダイレクトに味わった末に溢れてきた気付き、言葉。
言葉だけの「自然保護」や「SDGs」を語るのではなく。「与えられた体験としての自然」の表面をなぞるだけでもなく、身体の中の深いところで環境と自分自身を感じて味わって、言葉にする。
このゆりさんの「いったん、自分の中を通す」在り方は間違いなく生成AI時代に必要な「技術」の核心だと思うのであります。
そんな技術のわかりやすい第一歩はいつもと違う環境に身を置いて、その環境を全身全霊で感じること。はい、そんなわけで原っぱ大学に遊びに来ましょう(宣伝でした)。
これからのシーズン、めちゃくちゃ遊びが楽しいでーす!
原っぱ大学の最新スケジュールはこちらでーす。

未開の山の崖に張り付く…。アドレナリン全開。
すでに登録済みの方は こちら