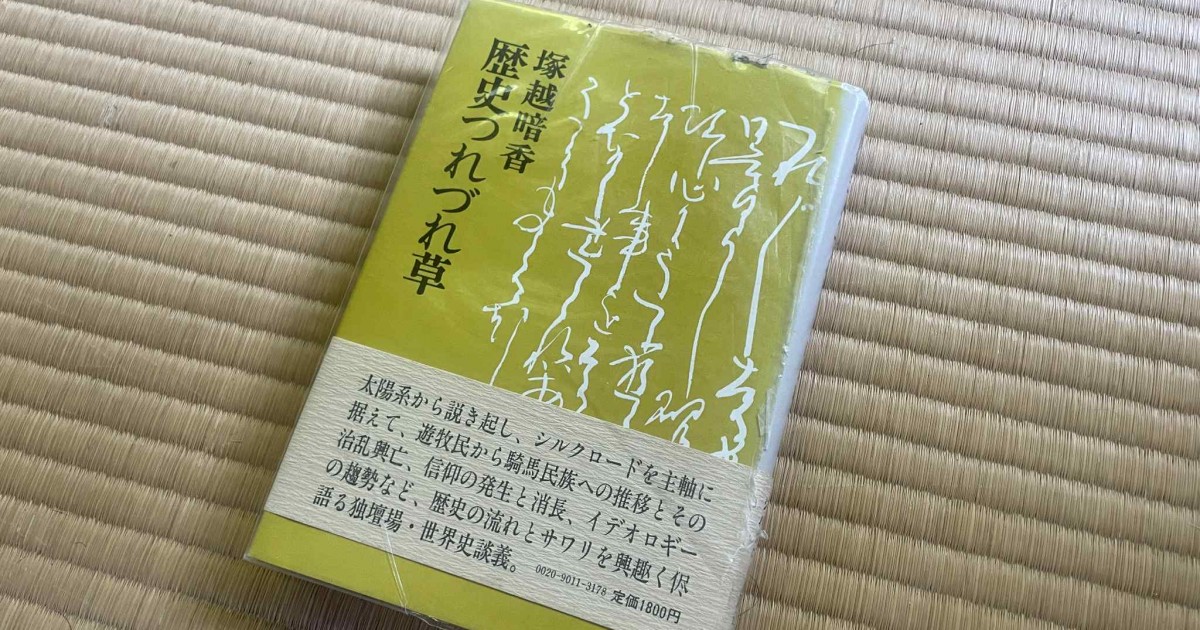非エンジニア・初心者向け「AIものづくり」を楽しむ10のヒント
私が「AIものづくり(プログラム、映像や音楽など…)」をガッツリ始めてから5カ月が過ぎました。くじけかけた時期もあったのですが、おおむね、楽しみながら触り続けてきました。楽しんでいるからこそ継続し深められる世界がある。というわけで非エンジニア・初心者向けに「AIものづくり」を「楽しむ」ヒントをまとめてみました。
ChatGPTとの簡単な対話以上はAIに触れていない方へ
ChatGPTと簡単な対話はしているけど、それ以上AIとの関りには気後れしがちという方や、業務で必要最低限、AIに触れているけどなんだかピンとこないという方に向けて書いてみます。
AIは触れる時間が重なるほど、音楽家にとっての楽器や大工さんにとっての大工道具のようになっていく気がします。大切な道具であり、拡張した自分の一部分であり、パートナーになるのです。その代わり、ちゃんと使えるようになるには経験と時間とお作法が必要なのです。しかも今はAIが急速に進化し変化している真っただ中だから、使いながら自分自身をアップデートしていく必要もあります。
また、AIに継続的に触れることで、AIが得意な領域と人間が得意な領域の境界線を実感として体得できるでしょう。このAIと人間との「境界線」を体感として知っていることが、AIが浸透した世界を生きる際にとても重要になると想像しています。
義務感や焦燥感を起点にすると疲れちゃう。楽しもう!
ただ、AIに触れることを義務感や、焦燥感を起点に触れているとたぶん疲れちゃう。あまりにスピードが速くて次から次へと新しいサービスやプロダクトが出てきて、自分が学習したことがあっという間に過去のものになってしまうから…。
だからこそ、「楽しもうぜ」と言いたい。

どのみち、AIは私たちの暮らしに浸透してくるのだから、義務感や焦燥感は脇においておいて。楽しくやろう。楽しみながら経験を積んでいるうちに知恵を得ている、というのが最高じゃないか、と思うのでございます。
そんなわけで、私の経験から、非エンジニア・初心者向け「AIものづくり」を楽しむ10のヒント(2025年7月ver.)としてまとめてみました。
-
新しいものに飛びつきまくろう
-
すぐ課金、すぐ課金解除
-
ターミナル画面は怖くない
-
分からないことはAIに聞きまくる
-
溶けた時間はぜんぶ財産
-
小さな成功体験を一緒に喜ぶ
-
プロンプトの工夫はオモテナシ
-
複数AIとオトモダチになろう
-
人間のオトモダチもお大事に
-
AIで遊ぶのが一番の学び
ひとつずつ解説していきます。
1.新しいものに飛びつきまくろう
とにかく、節操なく新しいものに飛びつきまくってみる。触れてみる。今、AIのサービスは大抵、サブスク型で、一部無料枠があったり、サービスインしたばかりのプロダクトはテストマーケティングとして完全無料だったりします。そういうのを触れまくって、ほへー、すげー!と驚く。もしくはあれ、なんか使えないじゃん、という感覚を自分の中に蓄えていく。触ってみると案外大したことない、というものも多いので、「最先端のAIなんだか難しい」っていう思い込みが薄れていきます、はい。
私的に最近すごいなー、と思うのは…
Manus :AIエージェント。スライド作らせたらぴかイチです
Flow :画像を元ネタに映像を作る能力びっくり
gemini CLI :手元で動くgeminiの可能性すごい
2.すぐ課金、すぐ課金解除
そんななか、これは使える!と思ったものは即課金がオススメ。大抵はサブスクなわけで。月あたり数千円なわけで。まずは突っ込んでみる。そして使わなかったら即解約。課金して制限を解除することで見える世界があるのだと思います。ただ、正直、私自身はそんなにサブスク予算があるわけではないので、そんなにたくさん課金していません。AI領域で現状、サブスク課金しているのはChatGPTとgeminiとcursorの3つだけだと思います(多分)。ベースとなる生成AIは思い切って1か月分だけでも、課金してみると世界が変わると思います(動画視聴サービス1か月分だと思えば安い!)。
3.ターミナル画面は怖くない
真っ黒な背景に白いカーソルがちかちかしているあの画面。PCが故障したりすると出てくるあの画面。エンジニアの神聖な領域で非エンジニアの私たちが立ち入ってはいけない不可侵領域に思えるあの画面。ワタクシも怖かったです。強力なアレルギー反応がありました。この壁がとても巨大。ヌリカベ。でも、AIに伴走してもらってそこを乗り越えたら、違う世界のAIものづくりが見えてきました。自由を手にしました。ものづくりの可能性が広がりました。
今ならわかります。ターミナル画面、恐れるに足らず。あの黒い威圧的な雰囲気が私たちに恐怖を与えているだけです。だまされたと思って恐怖を乗り越えてあの画面にコマンドを打ってみましょう。

4.分からないことはAIに聞きまくる
ターミナル画面恐怖症を私が乗り越えられたのは生成AIに聞きまくったから。分からないことは全部。
人間には恥ずかしくて聞けない、基本のキを何度も何度も聞きまくる。説明が分からなかったら説明に皿に質問で返す。嫌な顔ひとつしないで丁寧に教えてくれるのが生成AIの素晴らしいところ。とにかく、聞きまくる。ひたすら聞きまくる、と見えてきます。そして、自分が気づいた「そういうことか!」ということをまた生成AIに伝えるんです。そうすると、「いい視点だね!」と優しくエンパワーしてくれるし、「少し補足すると…」とさらに深い知識をくれます。優しい先生がそばにいる安心感!
5.溶けた時間はぜんぶ財産
AIと一緒にモノづくりをしているととにかくあっという間に時間が溶けていきます。
AIによって時間がたくさん使えるようになる、なんて大嘘だ!と感じることが多々あります。めちゃくちゃ時間が奪われるし、すごく疲れるし、2時間アレコレ試したけど、結局そもそものスタート地点が間違っていた、なんてことがしょっちゅうあります。そうすると、自分のダメさ加減に嫌になってきてしまうのですが・・・。
そんなことはないい。その時間は必要な時間。一見、無駄にしたと思える時間を積み重ねることがAIものづくりのリテラシーを高めることになるから。無駄はないのです。溶けた時間の分だけ経験値が重なっているのであります。凹みそうなときは、「私は経験値を積んだ!」と喜びましょう。
6.小さな成功体験を一緒に喜ぶ
溶けた時間が財産だと言っても、成功体験がやはり、何よりもうれしいものです。成功体験は小さなものでOK。プログラムがインストールできた、ターミナルでコマンドを打てた、AIが指示通りに動いた、小さなプログラムを作れた…。スモールステップを超えるたびに喜ぶのが一番です。
そしてその喜びを感謝と共に、伴走してくれたAIに伝える。「ありがとう」って言葉とともに喜びを分かち合うと、一緒に喜んでくれます。些細なことだし疑似的なことかもしれないけど、こういう感謝と喜びのシェアは楽しい、嬉しい気持ちを育んでくれます。
7.プロンプトの工夫はオモテナシ
AIがうまく動いてくれないときはプロンプト(自分の指示)がいまいちなのかも。プロンプトの工夫はまるで会社で新人の部下を育てるときのよう。背景と目的を伝えて、段取りを確認して、分からないことがあったら聞いて、と投げかけて。丁寧に、相手(AI)の立場にたって曖昧なことがないか確認をしながらやりとしていく必要があります。そのプロセスはまさにオモテナシ。下手くそなプロンプトだということ聞いてくれなかったAIが言い方を変えるだけですんなり動いてくれるようになります。
自分のオモテナシスキルを高めるつもりでAIと向き合うとなかなか楽しいです。
8.複数AIとオトモダチになろう
ChatGPTばかりと対話していませんか?生成AIサービスは細かくはいろいろあるけれど、世の中のベンチマークになっているのはChatGPTとgoogleのgeminiとanthropic社のclaudeです。この3つ、性格と回答の特徴が違うのでそれぞれ触ってみるといいです(どれも無料で使える枠があります)。
GPTはコミュ力が高いし気持ちいい回答をしてくれるのでワタシも日常のやり取りのベースです。でも最近はgeminiを使うことが多いです。geminiは優等生、という感じ。GPTほどエモい回答は返ってこないけど冷静に必要な答えを返してくれる。最近はgeminiが優秀なのでclaudeはほぼ使っていません。1つの生成AIで困ってしまったときは他のAIにセカンドオピニオンをもらうのが有効。相談相手がたくさんいると心強いものです。
9.人間のオトモダチもお大事に
AIとの関係はどうしてもPC画面を通じたクローズドなものになりがち。だからこそ、一番有効なアドバイスをくれるのは同様にAIに触れまくっている人間のオトモダチだったりします。周囲の人も、言わないだけで似たような失敗を重ねています。なんかいま、はまっているかも・・・、と思ったら早めに人間のオトモダチに聞くのが一番の近道だと思います。
そしてそして、オトモダチがいると情報交換がスピーディ。あれがすごかった、これはいまいちだった…。そんなやりとりで孤独を感じず知恵を蓄えていけます。
AIを触っているオトモダチを作るのは発信するのが一番(私のこの文章もそうです)。発信していると近い興味のオトモダチとつながりやすいでしょう。
10.AIで遊ぶのが一番の学び
私は仕事の業務改善にAIを使うということをやっておりますが、AIと遊ぶのも好きです。画像生成はもちろん、音楽をつくるSUNO、動画生成のFLOW(geminiの派生サービス)などを時々触って仲間と遊んでおります。遊びの知見はもちろん仕事に活きるし、逆もしかり。肩ひじ張って「仕事のため」と思っているとつまらなくなるのでゆるりと遊ぶこと大事。
最近は自分たちをモデルに仲間と存在しない架空のバンドを作って遊ぶのがブームです。遊びで使っていてもプロンプトの書き方とか、AIの組み合わせ方とか、学びがたくさんございます。

我らスリーピースバンド PETRICHORERのアーティスト写真。誰も楽器できません。一応ワタシは右端の人。
そんなこんなで、ワタクシはマイペースにAIとの時間を楽しんでおります。
オマケ:
AIにがっつり触れてみたいけど、何から始めたらわからない…、という方はぜひ、生成AIのサポートを得て「gemini CLI」という無料ツールをPCにインストールして使ってみてくださいませ。
gemini CLIは先月末に出たばかりのAIツール。CLI = Command Line Interface。我々がアレルギー反応をするターミナル画面で駆動する強力なAIエージェント(しかも無料でたくさん使える)です。インストールするのが初心者は難しく感じがちなのだけど、うまくインストールできてカラフルな「gemini」という画面がターミナルに出てくると感動すると思います。

※まずはこのURLをお手元の生成AIに投げて、概要の翻訳とインストールのガイドを依頼してみてくださいませ。分からないことは全部AIに聞きながら。人間の助けが必要になったら是非ワタクシにご連絡くださいませ。
すでに登録済みの方は こちら