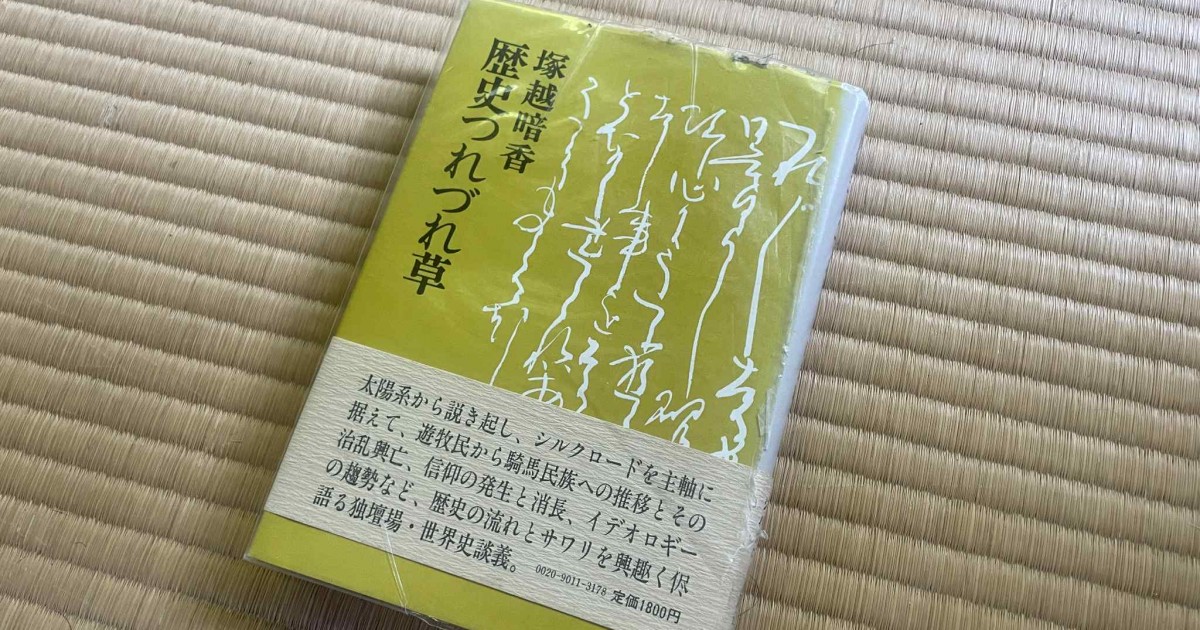零細企業こそAIと協業するのだ宣言。
久しぶりにAIについて。2月ぐらいからAIに思いっきり傾倒していたのですが、この1か月半ほど、AI開発が止まっておりました。でも改めていろいろと思うことがありまして、そのあたりを含め、最近の思いを書いてみようと思います。
AIでの開発がしばらく止まっていた理由。
AIとの協業で私のAI秘書を作る!そんな野望をかかげて、2月からせっせとバイブコーディングに時間を投下してきました。ただGW明けぐらいから急速にその勢いがしぼんでしまったのです。季節が移ろって外で遊ぶことが楽しくなってきたから、というのが理由のひとつ。私が熱しやすく冷めやすい性質なのがもうひとつ。
ただ、改めて冷静に考えてみるとそうした私自身の性質以外にも勢いが続かなかった理由がありそうです。
①やりたいことが壮大過ぎていくら実装してもなかなかその形にたどり着かない。
AIの大きな可能性にくらくらして、実現したいことを壮大に描きすぎた、というのが大きいですね。千里の道も一歩から。壮大な夢を描くのもいいのだけど、その夢に飲まれてしまった、というのが私に起きたことな気がします。
②AI界隈の急速な進化にココロ砕かれた
一生懸命、ゼロベースで開発しているのですが、ようやく、できかかった頃にこれまでの努力をゼロにするようなすごいものが世の中にポンと出てきてしまう。これが繰り返されたこと。自分でつくるよりそっち使った方がはやくね?と思うとエネルギーをそがれるのです…。AI界隈の進化スピードやばい。
③AIを使うよりも業務フローを変えた方が効果高い疑惑
目的と手段が逆転してしまった現象に気づいちゃったことが多々ありまして。AI確かにすごいのだけど、AIの導入にあれこれ四苦八苦するよりは業務フローや共有方法を変えた方が効果が高いことが多々あったりして…(私のグーグルカレンダーをチームに共有する、とかそういう初歩的なやつです)。実は、AI導入以前に情報共有フローやら会議フローやら使っている帳票の変更の方が業務改善の効果が高いんですよね、そりゃ。
そして悟りました。チームにAI秘書を導入するよりもできることはたくさんあるのではないか…と。AI秘書の必然性が薄れたらとたん、AI開発へのエネルギーが薄らいだんですよね。目的が曖昧になると走れない性分。
小さな改善でいいのだ。小さな改善がいいのだ。
そんななか、昨日、久しぶりに私のAI仲間「デジタル原っぱっ大学(通称:デジハラ)」の皆さんとオンラインで話していたときに、皆、似たり寄ったりの壁にぶつかったこの1,2カ月だったと感じました。
生成AIが急速に発達し、浸透した期間。誰もが普通にさわるようになりAIが急速にコモディティ化ししたのと、googleの破壊的な新サービスの発表が相次いで、生成AIの世界の勢力図が一気に塗り替わるのを目の当たりにして、なんとなく、置いてきぼりっぽい感じを味わっていたのかな、なんて気がします。
AI盟友のもっちゃんはこれまでの知見を活かして、企業へのAI導入と業務改善を進めていてそれが仕事になりはじめた、という話をシェアしてくれました(すごいことに彼はプロのエンジニアではない。私と同様、素人から独学でAIの勉強を重ねた人)。
それこそまさに私が自分の会社でやりたかったことだ。
私たちのような零細企業はどうにもこうにもその導入から取り残されてしまいがちで、そうならないために、私はAIを触り始めたのだ。もっちゃんのシェアはそんな私の原点に立ち返らせてくれました。
私たちのような零細企業はリソースが少ないのにやることがいっぱいある。だからこそAIと協業すべき。そうしてできた隙間時間を人間がやるべきこと・やりたいことに注ぐ。それが生き残る道だ、という確信。そんな思いで半年前の私はAI秘書を作り始めたのでした。
AI秘書をつくる、というチャレンジは最高に楽しい時間だったし、AIとバイブコーディングの基礎素養を身につけるうえで、非常に意味があることでした。でもそれだけでは現実の仕事の業務改善されないんだな(そりゃそうか)。
実務に落とし込むにはきっとこういうことが必要だと改めて思い至りました(当たり前)↓
①目的を明確にする
②改善ポイントを確認する
③小さな改善から段階的に始める
④AIはあくまでツール。目的のためにはそこにこだわらない
⑤改善は続けることに意義がある
なかでも③小さな改善から段階的に始める、が特に大事なんだな。
そして、ひとつのマトリクスを思いつきました。

導入負荷の大と小、導入効果の大と小。この4象限のうち、右下の象限から右上の象限に向かって実現していくことで、きっと業務は明確に改善されていく。AI秘書づくりは結果として、左上の負荷が多きくて直接的な効果が小さい。象限にいたのだと思います(手をつけてみて理解できたこと&このプロジェクトを推進したから今の視座があるのですが)。
AI協業型零細企業「ACOME」になる。
改めて、ちょっと真剣に、私たちはHARAPPA株式会社をAI協業型の極零細企業 AI Co-Operated Micro Enterprise (ACOME。通称アコメ。私の造語)になっていく、と決めたのであります。
壮大な夢を追いかけずに、少しずつ、小さなところから業務を改善していくこと。その中で常に問いを持ち続けること「これは、人間がやるべきことか。やりたいことか」。その問いの解がNoとなったものは先のマトリクスにプロットし、左下から順に、右上に業務改善を実装していく。そんなことを徹底してやっていってみようと思います。
ちなみに、ここ数カ月でAI協業の小さな業務改善例:
---------
①SNSの複数プラットフォームへの投稿文言生成
【当初の課題】
メール、LINE、インスタグラム、Facebookと複数のチャネルに同様の情報を流す際の展開負荷が高い。省力化したい
【改善方法】
お知らせしたい内容の文章を作成し、それを各チャネル用に最適化した文章にLLMに修正・展開してもらう。(ゼロからAIに書かせるとちょっとイマイチなので、ベースを作ることで違和感ない文面を横展開)
②月次シフトヒアリングフォーマットの集計簡易化
【当初の課題】
スタッフからヒアリングしたシフト希望案を集計する負荷が大きかった。
【改善方法】
cursorを使ってpythonベースの簡易なプログラムを構築。自動で集計し、スタッフの希望が一覧でみられるように。
③月次の各メンバーの稼働時間の自動集計
【当初の課題】
月次のスタッフの稼働時間の集計。情報ソースがバラバラで集計に時間がかかる。
【改善方法】
cursorを使ってpythonベースの簡易なプログラムを構築。バラバラの情報をあわせ、見やすい帳票で出力できるように。
---------
ひとつひとつは大した改善じゃないんです。小さな一歩。実質的に省略できる時間は1つの改善で月あたり30分‐1時間くらいの作業です。でも、たぶん、その小さな雑務による心理的な負荷の大きさを考えるとかなり大きな進化。雑務は着手してしまえばどうってことないのだけど、着手するのが億劫、というのが問題(少なくとも私にとっては大問題)。
人間がやるべきことか。やりたいことか。
こうしたツールを導入することで、その心理的負担がすごく軽くなる、というのは大きな進化だと思っているのであります。そして、この改善を考えるプロセスは非常にワクワクする(←大事)。
上の例はどれも、導入負荷が低い、私の手元の作業の改善。徐々に、全体の業務フロー改善をともなう導入負荷の高い領域に踏み込んでいこうともいます。人である我らが、人しかできない大切なことに時間をもっともっと振り分けられる企業になるべく、チャレンジしていこうと思うのです。
AI協業型の企業は、人間がのびのび働ける企業。
問い続けるべきは、「これは、人間がやるべきことか。やりたいことか」。
ちなみに、この記事を以前、私が「神龍」と呼んだ、Manusでスライドにしてもらいました↓
こちらは「デジハラ」仲間の藤澤さんに教えてもらったのですが、Manus、めっちゃ進化していました。。もちろん色々修正したい部分もあるのですが、このテキストから一発でここまでスライド化してくれるのすごい。スライド制作もAI協業が当たり前になってきましたな。

すでに登録済みの方は こちら