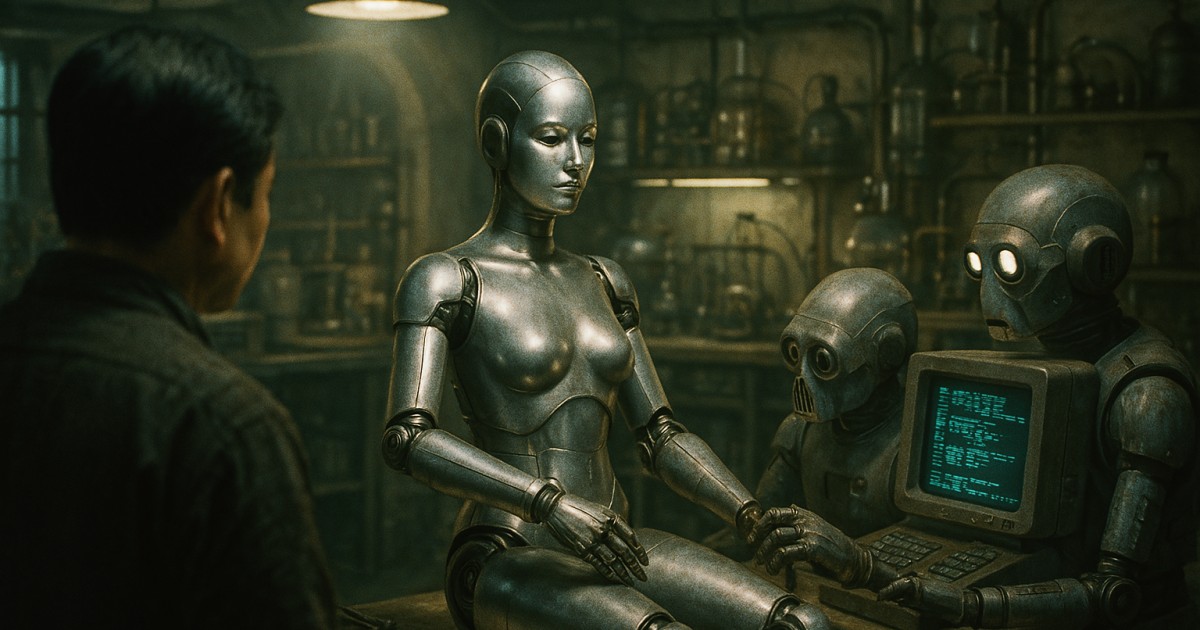特殊技能:縄文の肌感覚と令和の肥大化した承認欲求を併せもつこと。
意味不明のタイトルですね。意味不明なんです。このメルマガではおなじみの弊社の朝6時からのミーティング、通称「朝ミ」で今朝、私、ガクチョー塚越の「特殊技能」を言語化しようという話になりまして、結論、タイトルの通りになりました。今日はそんな「特殊技能」の話からスタートしてみようと思います(どこにたどり着くのかは不明)。
履歴書に書けるようなメソッドはありません
きっかけは共同創業者の志村が「原っぱ大学には『特殊技能』はあるのですか?」と聞かれたということをシェアしてくれたことでした。たぶん、質問をくださった方の意図は、私たちが「アウトドアなんちゃら認証」とか「なんとか認定アドバイザー」とか「ほにゃららファシリテーション公認」とかそういうタイトル的なものをもっているのか、そんな履歴書に書けるようなメソッドみたいなものがあるのか、という問いだったようです。
ただそういえば、私たちそういったタイトル的なものを持ち合わせておりません…。自分たちの感性と感覚と知恵を絞って、失敗しながら現場を積み重ねてきた、と。質問をくださった方はそうした「特殊技能」(≒タイトル)がなくて場が続いている原っぱ大学を不思議に思ったそうです。
そんな便利で分かりやすいタイトルはまるでもちあわせていないのですが、「特殊技能」はあるかもしれないということで朝から志村と慶ちゃんがガクチョーである私個人の「特殊技能」をあげてみよう、ということになりました(朝からちょっと嬉しい時間)。
嬉しい時間のはずが、二人からなかなか出てこない…。
縄文と令和のハイブリッドということざます
で、10分ぐらいうんうんいって、最終的に二人が出してくれたワタクシの「特集技能」がこちら(順不同)。
・足の裏が強い(いつも裸足、ビーサン、汚れてる)
・ありのままで存在している(ありのままとわがままの違いは何だ?)
・汚れても気にならない(感覚が縄文人。縄文人に失礼?)
・人の痛みに泣ける
・大きな怪我を回避できる(小さい怪我はしょっちゅう)
・ウニの棘が身体化している(鈍いあるいは強い)
・場のグリップ力
・掛け算が苦手(特殊技能ではない)
・ワクワクドキドキする嗅覚(場を感覚的にとらえる力)
・共感を呼ぶ言語化力(お、これは力っぽい)
・自分を晒す特殊能力(ある一定のところまでは自己開示)
・自分の肥大化した承認欲求を認めている
おお、たくさん出たではないか。大別すると・・・
■縄文時代の肌感覚
足の裏が強い/汚れても気にならない/大きな怪我を回避できる/ウニの棘が身体化している/ワクワクドキドキする嗅覚(場のグリップ力)
■令和時代の肥大化した承認欲求を認めている
自分の肥大化した承認欲求を認めている/自分を晒す特殊能力/共感を呼ぶ言語化力
■そのほか
人の痛みに泣ける/掛け算が苦手(特殊技能ではないと思う、これは)
ということになるようです。ということで今日のメルマガのタイトルです。
縄文と令和のハイブリッドということです、はい。正直、縄文が何なのかはよくわかっておりませんが、野性的なもの(肌感覚)と現代都市生活的なもの(肥大した承認欲求)を両方持っているということ。その間で揺れ動いている、というのはしっくりきますね、うん。「肥大した承認欲求」ってのは40代のオトナを表す言葉なかなかにお見苦しいですが、ここにあるものだから仕方ない。
「肥大した承認欲求」だっていいじゃない
だから何なんだ、ってことですが…。
これ、「原っぱ」そのものだなと思ったのです。「原っぱ」は都会の中の自然なんですよね。決して「サバンナ」でも「ジャングル」でも「標高6000mの雪山」でもない。生活の中にあって、現代の暮らしのなかにあって野性的な感覚を手にする場所。その調和、共存こそが私が原っぱ大学で生み出せていったらいいなと願っていることなのであります。
肥大した承認欲求と縄文時代の肌感覚が調和をとることによって、決して回顧主義や自然原理主義的に時代をさかのぼるのではなくて、令和の時代らしいバランスで、存在しあえる世界を作っていけたらと思うのであります。
「肥大化した承認欲求」とか言われるとある種汚い、未成熟な、忌避すべきもの、抑え込むもの、コントロールするものとジャッジしてしまいがちだけど、肥大して存在してしまっているのだから仕方ない。その存在を受け入れて、そのまんまに他者と共存していける世界に向かえたらいいな、なんて思うのであります。
「ゲーム」と「原っぱ」は縄文の肌感覚でつながる
話がだいぶ飛びます。テレビやスマホの「ゲーム」の話です。親として子どものゲームとの向き合い方はなかなか悩むことが多いようで、しばし話に出ます。原っぱ大学の参加者の子どもたちにはゲーム好きがすごく多いんです。
ワタクシ大前提としてゲームそのものは忌避したり制約したりするものではない、と考えています(だって楽しいもん!)。そして、ゲーム好きは山の中での遊び上手が多い、と感じております。山での穴掘りや基地づくりを「リアルマイクラ」(←マイクラ:マインクラフトというサバイバル・ものづくりのゲーム)とか呼んでせっせと好きに遊んでいます。
そうは言ってもあまりに日常的にゲームに夢中だったりすると「ゲーム依存症」にならないだろうかと不安になるのも親心だと思います。そんな「ゲーム依存症」の治療に自然での体験が有効だ、という話を聞きまして、そりゃそうだろうなと思うのであります。
「ゲーム」に没頭するのはなんでか、ということを原っぱ大学的目線で見ると、先に大人側の制約や先回りがあるんだと思うんですよね。街中でも公園でも学校や保育園や幼稚園でも。人に迷惑がかかるから、危ないから、ってことであれもこれも禁止にしてしまっている。失敗ができない、人とぶつかれない、汚れられない、冒険できない…。「縄文の肌感覚」を徹底して奪われてしまっているわけで。
バーチャルではあるもののゲームの中には「縄文の肌感覚」的な自由、チャレンジ、争い、失敗などを手にできる広がりがあるのだと思います。そりゃ夢中になる。
だから、日々、ゲームにいそしんでいる子どもたちを野に連れ出し、自由に遊んでいいことを伝えると、水を得た魚のように遊ぶのであります。友達とぶつかり合ったり、戦ったり、穴を掘ったり、木にぶらさがったり…。
「ゲーム依存症」に効くのはそりゃそうだろうな、と思うんです。
「ゲーム」と「自然」は対立するものではなく、同じ縄文人的欲求を満たしてくれるものだと僕には見えるから。自然で遊ぶ機会があればばそりゃ「依存」する必要はなくなりますわな。
我らの中にある「縄文の肌感覚」を過度に制約しないこと。これが現代人にとって大切な一歩になると思うのです。

追伸:と、これを書いているタイミングで「The Birthday」(元THEE MICHELLE GUN ELEPHANT)のチバユウスケさんが亡くなったとのニュースが流れました。ワタクシ、ミッシェル世代。当時、ミッシェルの尖った音はあまり好きじゃなかったのだけどThe Birthday は去年遅ればせながら出会って、生々しくて暖かくてかっこよくて久しぶりに「好きだー!」っていえるバンドになりました。短い期間だけどそれから随分と聴きこんでいて、ライブに行きたいと思い続けていたのに結局かなわず。悲しい…。ご冥福をお祈りします。
すでに登録済みの方は こちら